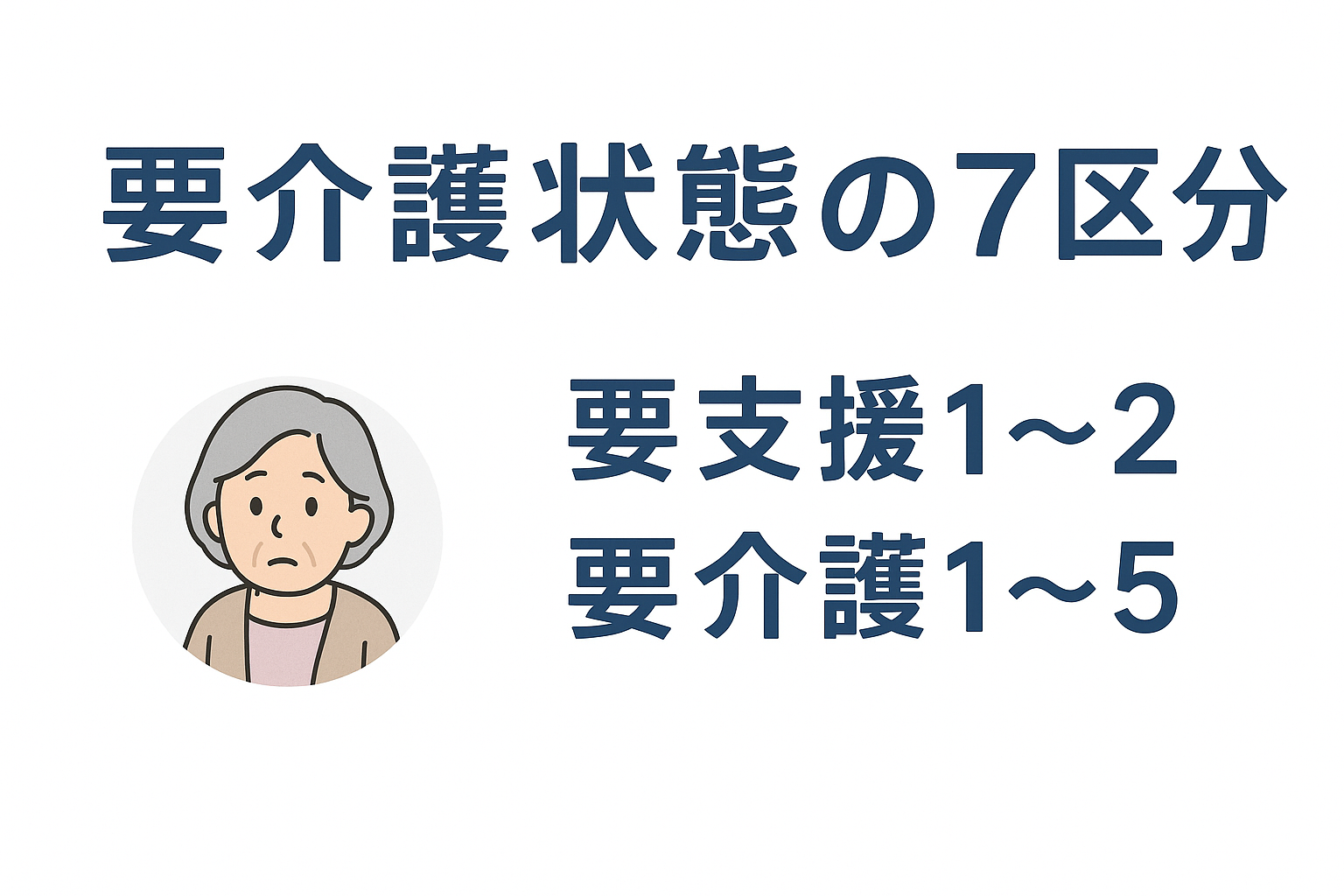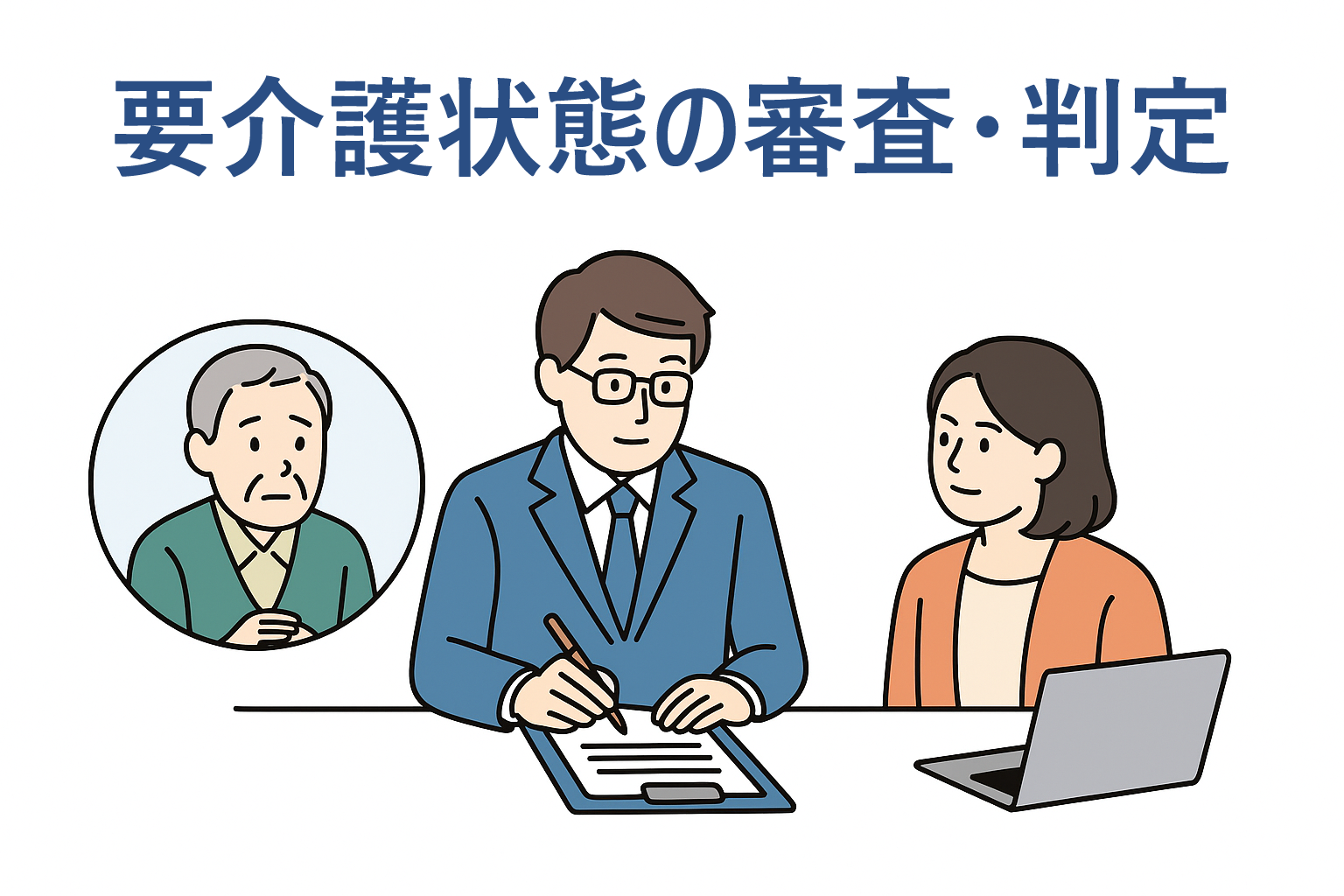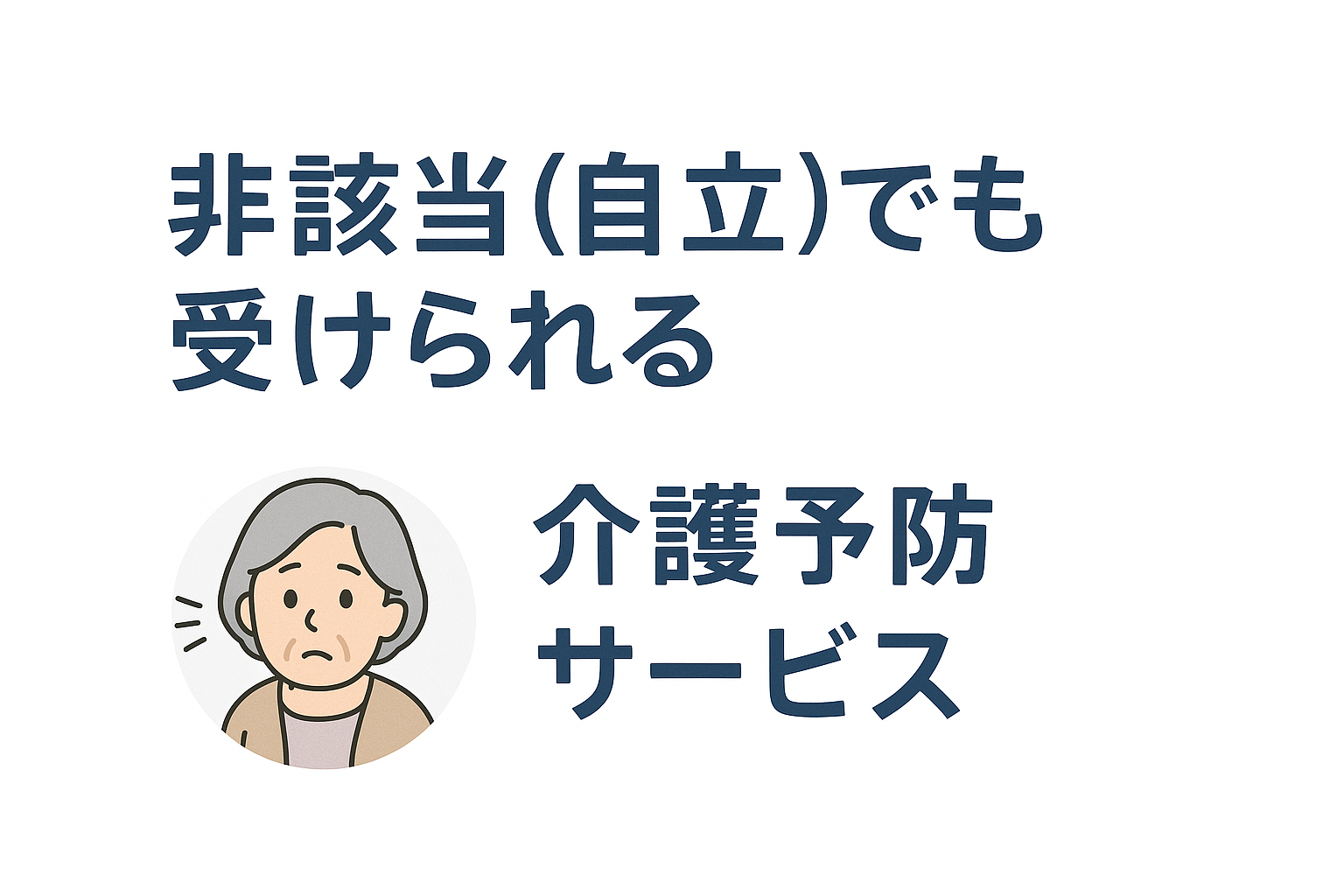介護保険制度では、利用者の心身の状態や日常生活の困りごとに応じて、7つの区分に分類して介護サービスの支給量を決めています。
区分は「非該当(自立)」を除き、「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階です。それぞれの区分には、日常生活での支援の必要性に応じた基準があります。
要支援1・要支援2の特徴と利用できるサービス
要支援1
- 基本的には自立しているが、生活の一部に支援が必要
- 例:買い物や掃除、ゴミ出しにやや不安がある
- 利用できる主なサービス:
- 介護予防訪問介護(ホームヘルプ)
- 介護予防通所介護(デイサービス)
- 配食・生活支援など
要支援2
- 日常生活の複数の場面で継続的な支援が必要
- 例:調理や入浴、衣類の着脱に一部介助が必要
- 利用できる主なサービス(要支援1に加えて):
- 介護予防福祉用具貸与
- 介護予防住宅改修
- 短期入所生活介護(ショートステイ)
要支援の段階では「介護予防サービス」が中心です。状態の改善や自立の維持を目指す支援内容となります。
要介護1~5の特徴と利用できるサービス
要介護1
- 部分的な介助が必要(例:入浴や掃除で見守りや一部介助)
- 利用できる主なサービス:
- 訪問介護、訪問入浴介護
- 通所介護(デイサービス)
- 福祉用具の貸与、住宅改修など
要介護2
- 日常的に複数の介助が必要(例:排泄や衣類の着替え)
- 要介護1に加え:
- 短期入所療養介護(医療ケア付きショートステイ)
- 訪問看護、訪問リハビリテーションなど
要介護3
- 常に何らかの介助が必要(食事・排泄・入浴など)
- 認知症による見守りが必要なこともある
- 利用できる主なサービス:
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 特別養護老人ホームへの入所も視野に
要介護4
- ほぼ全面的な介助が必要(歩行困難でベッド中心の生活)
- 要介護3までのサービスに加えて:
- 夜間対応型訪問介護
- 介護老人保健施設の長期利用
要介護5
- 常に全面的な介助が必要(寝たきりに近い)
- 医療的な対応も頻繁に必要になることが多い
- 利用できる主なサービス:
- 訪問看護・訪問介護の多用
- 介護医療院などでの生活支援
- 24時間体制の施設介護
区分の決まり方と更新
要介護度は、「訪問調査(74項目)」「主治医意見書」「介護認定審査会の審査」をもとに決定されます。
介護状態は変化するため、定期的な更新申請や状態悪化時の区分変更申請が重要です。
区分によって利用限度額も異なる
介護度が高くなるほど、介護保険で賄われるサービスの支給限度額が上がります。限度額を超えた場合は自己負担になります。
必要なサービスを見極めつつ、ケアマネジャーと相談して無理のない利用計画を立てることが現実的です。
【参考資料】
- 厚生労働省「介護保険制度の概要」
- 介護支援専門員実務研修テキスト
- 各市区町村の介護保険ガイドブック