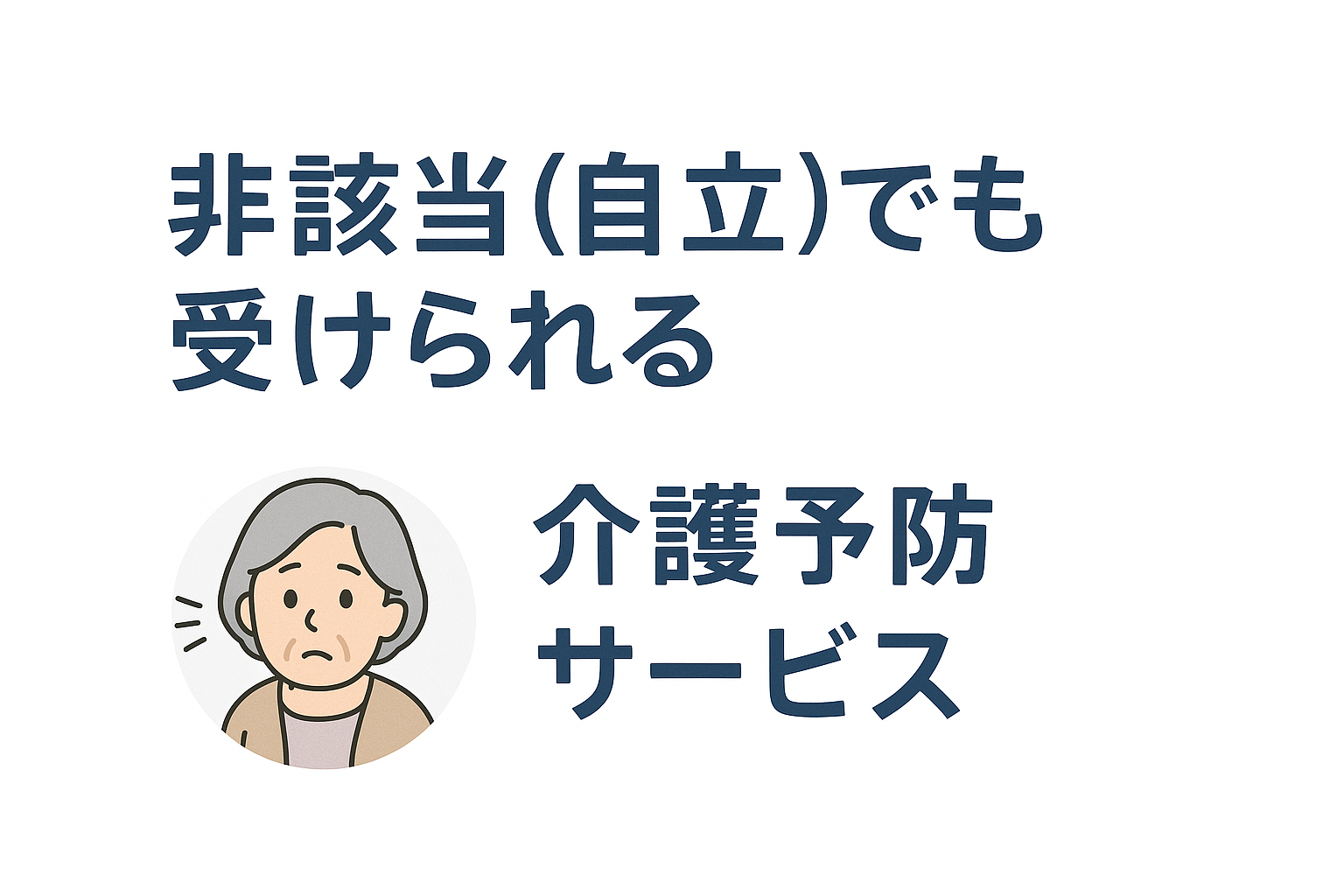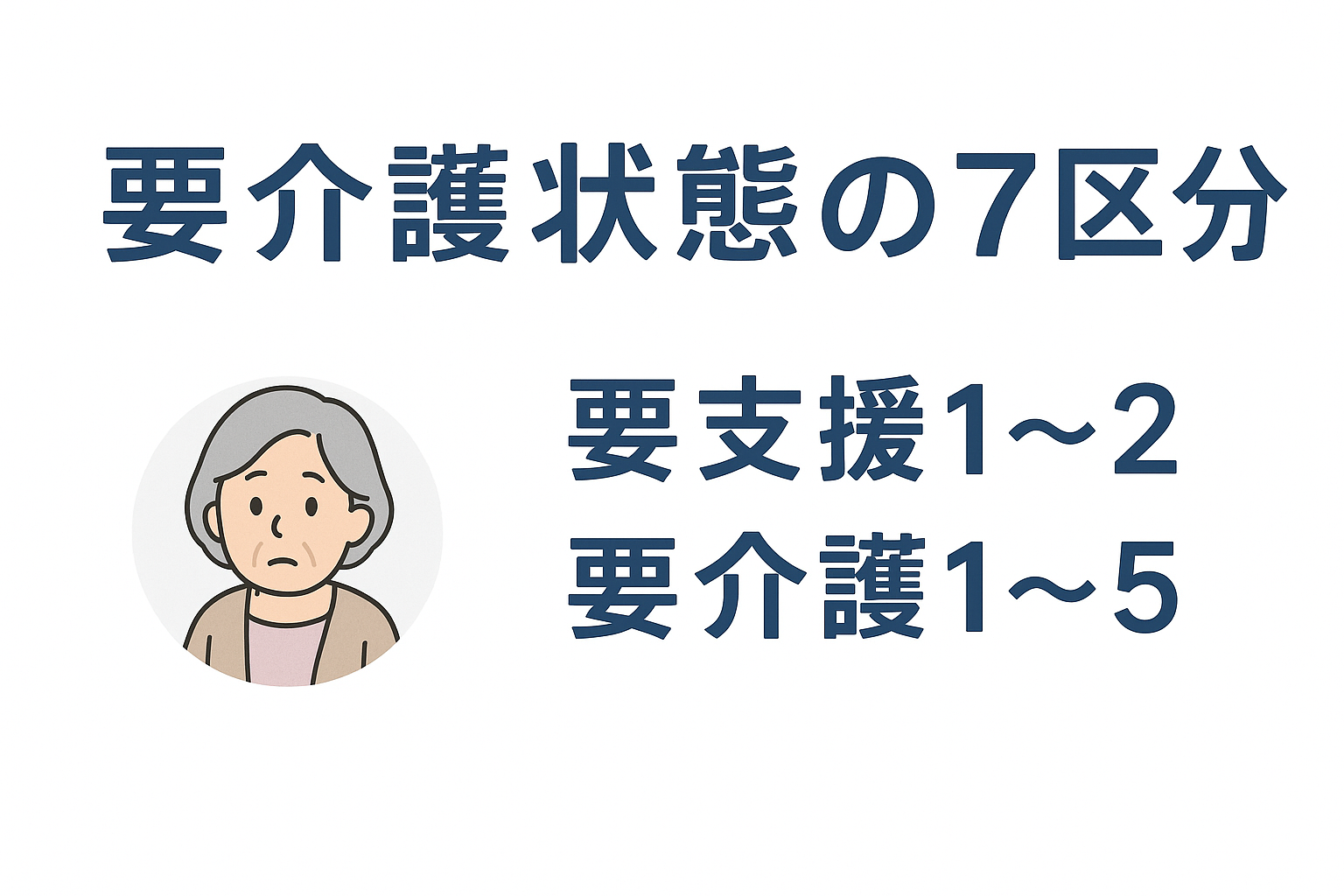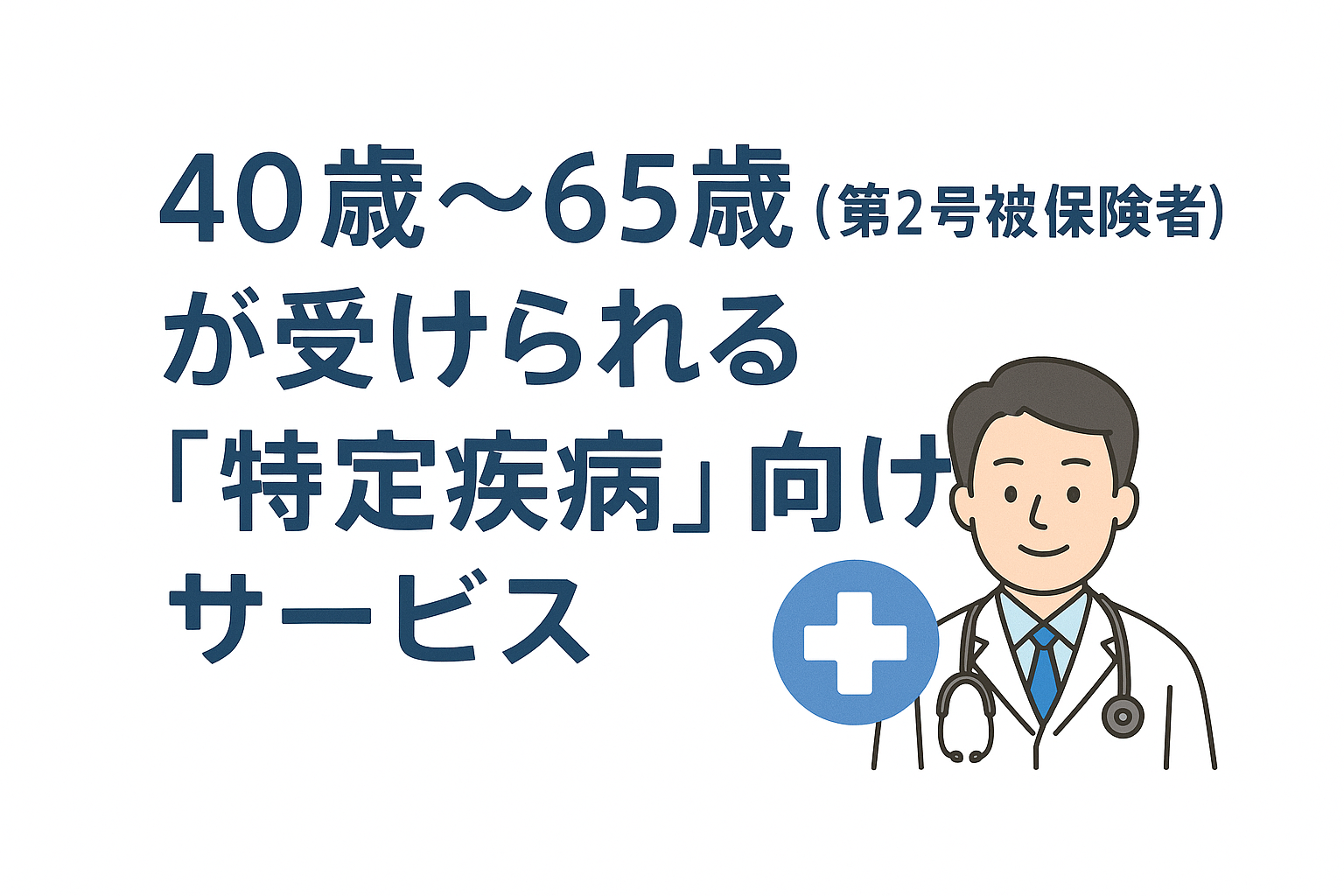介護保険の申請をした結果、「非該当」と認定されることがあります。これは、現時点では要支援や要介護に該当しない、つまり「自立」と判断されたことを意味します。ただし、自立しているとされても、高齢者のなかには日常生活で不安を感じている人や、将来的に支援が必要になりそうな人もいらっしゃいます。
そのような方々に向けた支援制度として、各市区町村で実施されているのが「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」です。
総合事業とは
総合事業は、2015年から本格的に始まった制度で、高齢者ができる限り自立した生活を続けられるようにするための予防的な支援を提供するものです。介護保険の枠組みの中で行われますが、要支援認定を受けていない高齢者も対象になる場合があります。
市町村が中心となって事業を組み立て、地域の実情に応じた多様なサービスが提供されています。総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2本柱で構成されています。
介護予防・生活支援サービス事業で提供される主なサービス
訪問型サービス
- 買い物支援や掃除、ゴミ出しなどを担う生活援助中心型のサービス
- 簡易な身体介助(外出支援など)も含まれる場合あり
- サービス提供主体は、事業者だけでなくNPOやボランティア団体も含まれることがある
通所型サービス
- 地域の通いの場(サロン、ミニデイ)での体操やレクリエーション
- 短時間のデイサービス形式もあり
- 社会参加や孤立防止に重点を置いた取り組み
生活支援コーディネーターの配置
- 地域の支援資源をつなぐ「支え合い」のしくみづくりを進める役割
- 地域包括支援センターと連携して、相談窓口や情報提供を行う
一般介護予防事業の内容
一般介護予防事業は、すべての高齢者を対象に、介護予防や健康維持、社会参加の機会を広げることを目的とした取り組みです。こちらは要支援認定の有無にかかわらず利用できることが特徴です。
主な取り組み例
- 介護予防教室(運動・栄養・口腔・認知症予防など)
- 地域サロンや趣味活動グループの開催
- ボランティア活動や地域づくりイベントへの参加支援
- 高齢者向け健康講座や市町村主催の啓発キャンペーン
こうした活動を通じて、高齢者の閉じこもり防止やフレイル予防、地域とのつながりづくりが進められています。
利用するにはどうすればいい?
利用の窓口は、地域包括支援センターまたは市区町村の高齢福祉課です。次のような流れで進みます。
- 簡易チェックリスト(基本チェックリスト)などで支援が必要と判断される
- 総合事業の対象者として選定
- 利用調整ののち、サービス提供開始
一般介護予防事業については、広報紙やホームページでイベント情報が掲載されていることが多く、申し込み不要で自由参加できる企画もあります。
利用者にとってのメリット
- 要介護認定を受けていなくても支援が受けられる
- 介護保険の正式サービスより柔軟な運用が多い
- 地域に根ざした取り組みなので、心理的な負担が少なく参加できる
- 将来の要介護状態の予防につながる可能性がある
注意点と確認しておきたいこと
- 総合事業は市区町村ごとに設計されているため、提供される内容や対象範囲に違いがある
- 一部サービスは利用料がかかる場合がある(介護保険と同様に1割~3割負担)
- 利用には一定の条件があるため、事前相談が重要
【参考資料】
- 厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン」
- 各自治体の介護予防パンフレットや広報紙