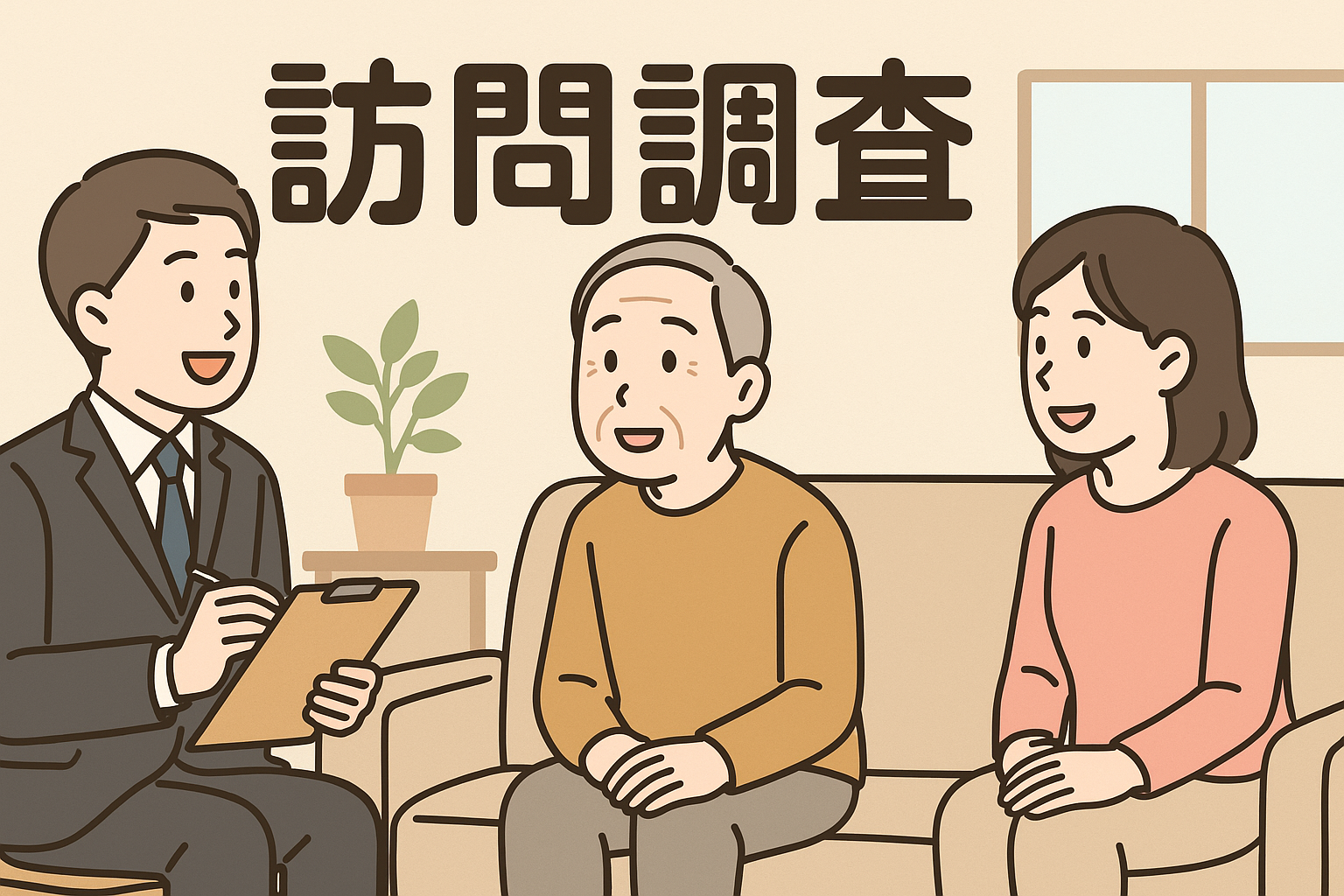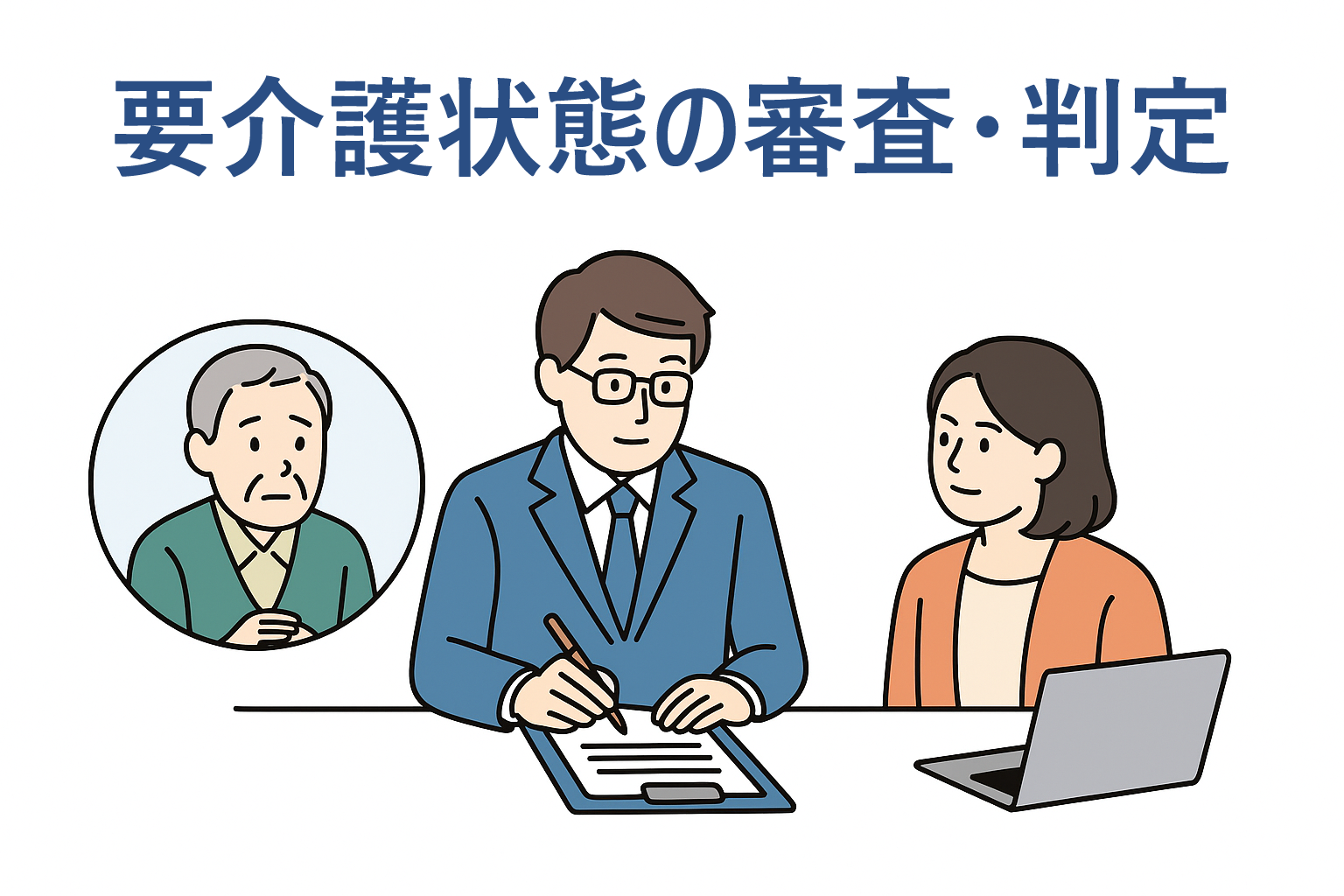介護保険サービスを受けるためには、要介護認定を市区町村に申請する必要があります。申請が受理されると、次に行われるのが「訪問調査(認定調査)」です。
調査員(市町村職員または委託された専門職)が自宅などを訪問し、本人の心身の状態について詳細に聞き取りを行います。この調査結果は、要介護度を判定するための重要な資料となります。
「訪問調査」の前に準備しておくこと
訪問調査をスムーズに受けるためには、以下のような準備をしておくと安心です。
- 本人の状態を整理しておく
- どんな動作ができて、どこで困っているのかを家族と共有しておく。
- 転倒歴、持病、服薬状況なども把握しておくとよいです。
- 主治医や病院情報の確認
- 調査後に主治医意見書の作成が必要になります。病院名・医師名・電話番号などを控えておきます。
- 家族が同席する場合は役割分担を
- 本人が答えづらいことや忘れてしまいがちな内容は、家族が補足できるよう準備しておきます。
認定調査票の構成とは?
訪問調査は「認定調査票」に基づいて進められます。これは全国共通の調査票で、以下のような構成になっています。
基本調査(74項目)
移動、食事、排泄、入浴、着替えなどの日常動作に関する具体的な質問のほか、認知症状、精神・行動面、過去14日以内の特別な医療なども含まれます。
- 身体機能や動作について(起居・歩行・視力・聴力など)
- 生活機能について(食事、排泄、入浴、更衣など)
- 認知機能について(認知症、徘徊など)
- 気持ちや行動について(認知症の周辺症状)
- 社会生活について(お金の管理や買い物、人間関係など)
- 過去14日間に受けた医療行為について(点滴や経管栄養など)
特記事項
- 基本調査ではカバーしきれない個別事情や補足事項を自由記述。
- 家族の介護状況や生活環境などもここで補足される。
実際に聞かれることの例
訪問調査では、以下のような具体的な質問が行われます。
- 「一人でトイレに行けますか?」
- 「食事の準備はご自身でされていますか?」
- 「最近、転んだことはありますか?」
- 「今日が何日か分かりますか?」
- 「通院や薬の管理はどうされていますか?」
回答は「できる」「一部介助」「できない」などの選択式で行われます。答え方によって要介護度の判定に影響があるので、普段の状態に基づいて正確に答えることが重要です。
調査時に注意することは?
- 基本的に本人が答える
- できるだけ家族は割り込んだり先回りして答えたりしないようにします。
- 本人の回答が実態と異なる場合も、その場では否定せず後で調査員に伝えます。
- 実際より軽く見せない・重く見せない
- 調査は“現状把握”が目的なので、正直に答えることが大切です。
- 服装や部屋の状態もできるだけいつも通りにしておくのがよいです。
- 日常の一番大変な状態を基準に答える
- 体調が良い日ではなく、平均的または悪い日の様子を中心に説明すると適切です。
- 調査員に状況を説明しやすくする
- 家の段差や生活動線を見てもらうことで、生活上の支障も伝わりやすくなります。
- 本人が認知症の場合、家族が適切に補足する
- 質問の意図を理解できない場合など、家族が状況を補完することが必要です。
まとめ
訪問調査は、要介護認定において非常に重要なプロセスですので、普段の暮らしの中で困っていることを正しく伝えるために、事前に準備しておくとスムーズです。
調査が終わった後は、主治医の意見書とともに審査会での判定へと進みます。わからない点は、地域包括支援センターなどに相談しながら進めていくと安心です。
【参考資料】
– 厚生労働省「介護保険制度の概要」
– 各市区町村の要介護認定の手引き・訪問調査の案内ページ